すべては煙草である

2015年になってすぐに、喫煙をやめた。いわゆる禁煙だ。
もう一ヶ月以上経っている。数日前、いつもの通勤でマンハッタンを縦につらぬく地下鉄1番線に乗ったら、あろうことかホームレスの方が車内で煙草吸ってて、素敵な臭いが充満する車内で「あ、これはやばいな」と思ったし、実際少しは喫煙していた頃を思い出したけど、ものすごく吸いたくなったりはしなかった。
つまり、恐らくこの禁煙は成功したのだろう。もう一生喫わないで済みそうな気はする。
何しろ20年以上、煙草を中心に生活してきたと言っても過言ではない。
私のようなひどいヘビースモーカーだと、どこで誰と話していても、何をしていても、基本的な行動は次にどこで喫煙できるか、ということを意識して行われる。
仕事でも困ることはたくさんある。打ち合わせなどが2時間以上続くと、頭の中のかなりの部分が自分が喫煙しているイメージで埋め尽くされる。それにより、打ち合わせの序盤ではキレキレのアイデアと適切でいて冒険心のあるディレクションをビターンと展開してカッコいい広告クリエイターを演じることができていたにもかかわらず、後半は虚ろな目で「煙草喫いてえなー」以外のことはあまり考えず、発言もせずボーッとすることになる。
筆者は海外で仕事をしているので、会議というものは大体英語だが、当然母国語ではないのでニコチンが切れるとみんな何言ってるのかがよくわかんなくなる。「屈強なプロレスラーが地下鉄の中で戦いながらパソコンの宣伝をする」みたいな話だと理解していたら、実は「地下鉄のデジタルサイネージに表示する映像をプロレゾ(映像のタイプ)で納品する」という話だったりとか、そういうとんでもない間違いが頻発し、仕事にならなくなるのだ。
煙草を喫っていない私などは、炭酸が抜けてぬるくなったコーラみたいなもので、何の役にも立たない。その状態においてはチーフ・テクノロジー・オフィサーなどという肩書きは噴飯物なのであって、能力の0.2%くらいしか発揮していないと言っていい。

いやそもそも8.5年前くらいに今の業界に来てから、自分の能力なんてまともに発揮したことがない。それまで通っていた出版社のデスクでは、21世紀においてはかなり稀少な存在ではあったけれども、みんな喫煙していた。あれこそが自分の力を100%発揮できる職場環境なのであって、「デスクでは禁煙」という一般的な環境で仕事をする場合、仕事をしている時間というのは喫煙所と喫煙所の間に存在するつなぎの時間になってしまうし、つまり仕事というのは喫煙していない余った時間にやるものとなる。
いま働いている世界でそれなりにいろいろつくってきたけど、何か未だ振り切れない感じがしていたのはデスクで煙草が喫えないからで、それさえできていれば今頃はダン・ワイデンとかヘガティ卿とかリー・クロウとかと並んで広告界のレジェンドとして表彰されているはずだ。JUST DO ITだ。
大なり小なり喫煙者というのはそんなようなものなのであるが、とにかく20年以上それでやってきてしまっているのだ。どういうことかというと、たとえば私は非喫煙者として働いたことが無かったし、非喫煙者として嫁と接したことが無いし、当然非喫煙者として父親であったこともない。主だった活動は、だいたい喫煙者として、喫煙と喫煙の間にやってきたものだ。10年前、嫁の親に「ま、真紀さんをください!」なんて言い放ったのですら、喫煙と喫煙の間に行われた行為なのだ。
そんな人物である私の禁煙なわけであって、この1ヶ月余、私は相応の喪失感と脱力感に苛まれて生きてきた。
喫煙を止めた人というのは、おしなべて喫煙習慣を否定する。ともすれば喫煙者を罵倒する。その感覚は結構分かる。喫煙習慣というのはある種「突っ込みどころ満載」の習慣である。身体にとっては本当に全く何も良いことがないわけだし、臭いはつくし、いろんなものの途中に席をたつ必要があるし、実にどうしようもない。
煙草というのは、否定しようと思えばいくらでも否定できるのだ。むしろほとんど否定要素しかない。
だからこそ、みんな煙草を否定して嫌いになって、やっとこさどうにか喫煙習慣とお別れする。もちろんそれは有効な方法だ。
私も煙草をやめようとしている。しかし私はそのために喫煙というものを否定して良いんだろうか?
喫煙というものが一番厄介なのは、それが人間の「平均幸福」の実現難易度を上げてしまうからだと思う。
「平均幸福」とは何かというと、その人が日常生活において平均的に享受している幸福のことである。すごい簡単に言うと「ふつう」っていうことである。
幸福感が「平均幸福」の状態を上回ると人間は「あー幸せだなー」と思い、「平均幸福」を下回ると、「あー不幸だなー」と感じる。
例えば、箱根にでも行って温泉につかってその後にコーヒー牛乳を飲む。これは現在の私にとっては超幸せな状態である。なぜかというと、私はいまニューヨークに住んでいるので、箱根の温泉などは、極端な非日常で、もはや「夢」に近い存在だ。東京に住んでいる人にとっての自由の女神みたいなものだ。いや、身体に作用する分、自由の女神どころではない。
しかし、箱根の旅館に住んでいる人にとってはどうだろう? この人たちは毎日温泉につかってコーヒー牛乳を飲んでいる。つまり、それが日常であり、「ふつう」なのである。そんな箱根民が、突然何かの都合で温泉に入れなくなったらどうだろう? その状態は「ふつう」の状態より「温泉に入れない」という凹み要素があるぶん、「不幸」になってしまうのだ。
繰り返しつつ簡単に言うと、温泉が特別なものである私にとっての普通の状況(温泉に入れない、という状況)が、いつも温泉に入っている箱根民にとっては不幸な状況なのだ。
これが煙草である。温泉を煙草に置き換えるだけでOKだ。
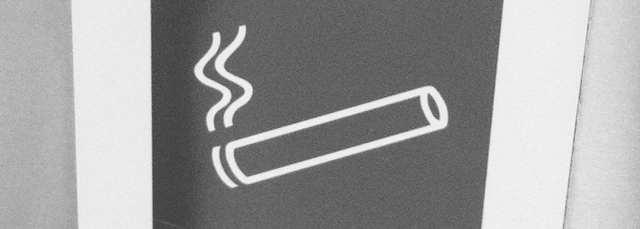
喫煙者にとっては、「しょっちゅう煙草吸ってる状態」が日常だ。その人たちにとっての「平均幸福」は、煙草を吸っている状態であり、喫煙者というのは煙草が吸えないとイライラするし機嫌が悪くなるし、要するに不幸になる。
しかし生きていると煙草を吸えない状況というのはたくさんある。煙草が「平均幸福」を上げてしまっていることで、喫煙者は不幸になりやすくなってしまっている。これが喫煙がもたらす最大の困った事象だ。
これが、私が煙草を止めて、喫煙というものをほぼ初めて客観的に評価して理解したことだ。そして、その前提で周囲を見回してみてわかったことがある。
それは、「世の中全部煙草じゃないか」ということなのである。
自分にとって一番わかりやすいのは国際広告賞である。自慢ではないが、といいつつある種完全に自慢にしかならないが、私はアジア太平洋広告祭というアジアのナンバーワン広告を決めますよという国際広告賞のデジタル部門で、たぶん2006年から5年連続で最高賞、つまりその年最高のデジタル広告に与えられる賞を受賞していた。
これは、今考えるとありえないことである。特に、近年は審査員をやることも多くなってきたので、それがどれだけデタラメに大変なことかがよくわかる。最高賞とか、取るのメチャクチャ大変なのである。
しかし恐ろしいもので、4年とか5年連続でとっていると、その状況が自分にとっての「平均幸福」になってしまい、賞を取らないことが恐ろしくなる。賞をもらわないという状況が不幸に感じられるようになり、賞をとることは幸福というより、「安心」みたいな感じになる。幸福状態のハードルがものすごいところまで上がってしまう。
余談だが、実際にそういう連続受賞なりがストップしたらしたで、禁煙と同じでしばらくするとどうということもなくなるし、今年に至っては面倒くさいし、ものによってはダサいし、お金かかるから、ちょっとしか広告賞に出品してなかったりする。
もう、生きていると全部コレである。小学校のとき、私は四谷大塚といういわゆる中学受験向けの進学塾に行っていて、これがえぐいことに毎週全国テストみたいのがあって順位がでるシステムになっていた。そんなもの無くても良いのに、なぜかそういうものが世の中にはあって、うちの母親はこれにのめり込んだ。
私がその塾で毎週平均的にキープする全国順位が母にとっての「平均幸福」になって、たまにそれを下回ろうものなら大騒ぎだ。罵倒され、教科書を窓の外に投げ捨てられ、テレビもゲームもすべて禁止された。優しかった母は豹変した。
しかし、なぜ母は豹変してしまったのかというと、私が四谷大塚である程度の実績をキープしたがゆえに、「平均幸福」のハードルが上がってしまい、それを希求する禁断症状の強さが小学生の子供に対する常識的な態度を大きく超えてしまったということなのだ。
天一のこってりラーメンを食いたい。良い音楽を聴きたい。良い家に住みたい。かわいい彼女と付き合いたい。
すべて煙草と同じだ。人間はこれらがなくても死にはしない。

そして私にとってこの概念における究極は、家族だ。どう考えても家族が一番大切である。嫁がいて、二人の息子がいる。自分にとって嫁以上のパートナーは絶対にいないというか、嫁ほどに一緒にいてストレスが生じない人間などいない。息子たちに至っては、はっきり言って便意のようなものを催すほどかわいい。見たり、話したり、一緒に遊んでいるだけで前立腺のあたりがむずがゆくなってしまうほどだ。
彼らを失うことは自分にとって死に等しい。想像したくもないし、ここにそんなことを書くのもためらわれる。
しかし、家族だって煙草と同じだ。家族がいなくっても、その人にとっての「平均幸福」は確実にある。家族などというものがあるから、家族がいない場合の不幸度がものすごいレベルになってしまうのだ。そう考えると、家族を持つということは、人間にとってとんでもないリスクだ。
そして、もっと突き詰めると、「生きること」そのものが煙草なのかもしれないし、
生きる中ででくわすすべての煙草的なものを除いて、からっぽにした状態のことをたとえば茶道における「虚」と言うのではないか(その場合は、また何かをそこに入れるという意味において「リセット」に近い感覚かもしれない)、そしてその先に「悟り」みたいなものがあるのではないか、とか結構真剣に考えるようになった。今年に入って、煙草を止めて七転八倒しながらそこに至った。

そして私は煙草を肯定することにした。
私はいろいろ恵まれた状態にあって、かなり「平均幸福」のハードルが高い状態なのだと思う。
私は先進国に生まれて先進国に移住した。家族と別離するのは嫌だ。ラーメンも食いたい。良い音楽を聴きたいし、いろんなところに旅行したい。広告賞も前ほど欲しくないけどもらえるんだったら欲しい。煙草を否定することは、そういったものをすべて否定することになってしまうような気がするのだ。
こういうものを何か言葉で表すとしたら、「文化」ということなんじゃないかと思う。人間は社会をつくって、いろんな「文化」をつくる。全部、無駄で煙草みたいなものだ。けど、私はそんな文化を美しいと思うのだ。そして、喫煙所で交わされる喫煙者同士の時間限定の会話も、道で漂う紫煙の香りも、新幹線の喫煙者の阿片窟みたいな不健康な空気も、全体的にかっこいい「文化」だと思うのだ。
立川談志は、落語の真髄を「業の肯定」と定義した。それが概念としてかぶるのかどうかはわからないけど自分にとってそれは、煙草みたいな「否定しがいのあるもの」を認めてあげることのように聴こえるし、「文化から逃げない」ということなのではないかととれたりする。
じゃあやめなくてもいいじゃん、という話ではあるが、そういう意味では上記の家族という別の「煙草のようなもの」がより大事ではあるし、年末に禁煙経験者である同僚の室市さんから「カンタさんはタバコやめたら次のレベルに行ける」と言われたのがかなり引っかかって、やめることにした。
次のレベルというのが仕事のことなのか、なんのことなのかよくわからないが、世の中を上記のように理解できたのは1つの収穫だったかもしれない。
とにかく、私はやめることにしたけれど、煙草はとても素敵なものだ。
何せ、これは死ぬ前に自費出版か何かで自叙伝でも書くときに書けば良いんだろうけど、煙草を喫っていなかったら嫁と出会っていないし、家族と出会っていない。
=======================

私が煙草をやめるかやめないかのタイミングで、若井信栄さんが亡くなった。私の父は私が生まれた頃から現代詩をつくっていて、若井さんはその仲間だった。
子供のころから現代詩に囲まれて育つという、異常な環境ではあったけれど、私には詩のことなどよくわからず、若井さんはたまにやってくる「変なおじさん」だった。「家族ぐるみで付き合っている父親の友人」というのは誰でも何かしら思い浮かべることができるポジションのような気がするが、私にとっての若井さんはそれだった。一緒に旅行に行ったのは一度や二度ではないし、実は私にとって最も古い記憶は、若井さんが家に来たときの記憶だ。恐らく3歳の頃で、なぜか、若井さんが私達が住んでいたアパートにやってきた日の夜、アパートの窓の格子にくっついたプラスチック製の緑色の帯、というのが、私が自覚している最古の記憶だ。それは本筋には関係ないけれど。
若井さんは、恐らくうちの父よりもラディカルで活動的で、積極的にいい加減な人だった。「いい加減」であることに美しさを見出して、そこを志向しているように見えたから、「積極的」なのだと思う。
それは、少年だった私にとって季節ごとにやってくる「文化」だった。若井さんは、やってくるたびに何か無駄な、「煙草のような」ものを私に仕込んで帰っていった。
私はいわゆる「クリエイター」とか言われる商売をしていて、何がしか物をつくって世に問うことを生業にしている。
それらの生産物は恐らく、本来世の中に存在しなくても良いものだ。そしてとても刹那的なものだ。仮に人類の歴史に残るレベルのものをつくったとしても、将来、必ず人類は滅ぶし、地球はなくなってしまう。それでも、刹那的でも良いから「文化」をつくりたい。それはとても愉快なことなんだ。それを想うとき、私は無意識に若井さんのように振る舞おうとしていた。
締めくくりがものすごく不謹慎になるけれど、若井さんがこの世を去り、私の喫煙習慣も私から去りつつある。
若井さんが行ったあの世は、今までのあの世よりもちょっとだけ面白いんだろうなと思う。
若井さんに教えてもらった「文化」に敬礼しつつ、あの世の若井さんには、私の代わりに煙草を喫いまくってもらえたらと思う。
完全に何を言いたいのかよくわからなくなってきたが、その混沌もまた、若井さんを悼む文章にはふさわしい、ということにさせて頂く。ありがとうございました。
